児童虐待(疑い)の初期対応について
児童虐待とは、保護者が自分が養育する18歳未満のこどもに対して行う次の行為のことを言い、「いかなる人も児童に虐待をしてはならない」と児童虐待防止法や児童福祉法などの法律で定められています。児童虐待は、こどもの成長を妨げ、こころの病気の原因となる深刻な問題です。
| 身体的虐待 | 児童の身体に外傷または外傷が生じるおそれのある暴行を加えること。 |
| 性的虐待 | 児童にわいせつな行為をすること・させること。 |
| ネグレクト(育児放棄・育児怠慢) | 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や長時間の放置、保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 |
| 心理的虐待 | 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応をする、児童の目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)などその他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
地域で発見した場合
かもでいいんです
ご近所などで「虐待かも」と気になったら、すぐにお電話ください。
- 児童相談所虐待対応ダイヤル 189(イチハヤク)※24時間年中無休
- 子ども未来課 子ども家庭係 0192-54-2111 ※平日8:30~17:15

通告の義務
通告とは、個人が特定できる虐待に関する情報を児童相談所や市町村の担当部局に知らせることで、相談や情報提供なども含まれます。児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、すべての人に通告する義務が定められています。
平成16年児童虐待防止法改正法により、通告の対象が「児童虐待を受けた児童」から「児童虐待を受けたと思われる児童」に拡大されました。ですので、「かも」でいいんです。
また、児童虐待の通告により、秘密漏示罪や守秘義務違反、個人のプライバシーの侵害を問われることはありません。通告をした人が特定される情報は漏らしませんのでご安心ください。
通告(児童虐待の相談・情報提供)の内容
見た・聞いた事実をお知らせください。通告をする人(通告者)が、どの虐待にあてはまるか、またはしつけか否かを悩む必要はありません。「虐待かも」と思った様子やそのこどもの情報について、わかる範囲でお知らせください。次のような内容を確認させていただきます。
- どのようなことがあったか(自分で目撃した・声や物音を聞いた・人から聞いた)
- 人から聞いた場合、その人はこどもとどのような関係か
- いつ・どこで・頻度・そのこどもを最後に見かけたのはいつか
- こどもの名前、年齢または学年、性別、特徴など
- こどもと通告者の関係
- こどもの保護者や同居家族、家を出入りする人などについて
- こどもの住所や家の場所
- 通告者への再度の連絡など今後の協力の可否
通告者の氏名や連絡先の提供は任意となっています。匿名の通告も可能です。
通告を受け付けましたら48時間以内にそのこどもの所属機関や家庭訪問でこどもの安全確認を行います。その後、事実確認などの調査を行い児童虐待と判定した場合は、必要な支援や保護者への指導などを行います。
虐待の背景には、経済的問題やこどもに発達の問題、保護者自身の育ちの問題があることも多くあります。通告をすることは、こどもを虐待から守るとともに保護者の育児の悩みを解決することにもつながります。
学校・保育施設・放課後児童クラブ等で発見した場合
学校など、こどもが所属する機関では、児童虐待を発見しやすい立場にあるため、早期発見や予防、児童虐待を受けたこどもの保護や自立支援について、関係機関へ協力を行うよう努め、虐待を受けたと思われるこどもについては通告する義務があると定められています。また、こどもや保護者に対し児童虐待防止のための教育または啓発を行うことが求められています。
日頃からのこどもの観察、保護者との関係性の構築に加え、保護者に対して「暴力は許さない」というメッセージを発信することも大切です。児童虐待予防のためのリスクチェックリストなどを活用したり、発見した時の流れや対応における役割についても確認しておきましょう。
また、こどもは、自分から訴えた場合であっても、保護者をかばうことがあります。訴えを聞いた時は、「話してくれてありがとう」「こどもには、守られる権利があるんだよ」というメッセージをこどもに伝えましょう。
暴力を受けているかも
こどもの体にアザを見つけるなどした
 明らかな外傷(打撲傷、内出血、骨折、刺傷、やけどなど)がある場合は、児童相談所または警察への通告が第一選択肢です。児童相談所や警察への通告を迷うときは、子ども未来課へご相談ください。保護者の同意は問われません。
明らかな外傷(打撲傷、内出血、骨折、刺傷、やけどなど)がある場合は、児童相談所または警察への通告が第一選択肢です。児童相談所や警察への通告を迷うときは、子ども未来課へご相談ください。保護者の同意は問われません。
- 四肢の内側や陰部や臀部、わきの下などの引っ込んでいる部位の外傷
- 物体の形を思わせるような不審なアザ
- 境界線がはっきりしているやけど
- 乳幼児の口腔内のやけど
などは、身体的虐待が疑われます。
乳幼児の場合は、言葉で訴えることができないことが多いので、おむつ替えの時など注意深く観察しましょう。0歳~3歳で死亡リスクが高くなります。
いつも怒鳴られたり、自尊心を傷つけられているかも
こどもに気になる言動がある
明らかな外傷はないけれど、こどもが「家に帰りたくない」などこども自身が保護や救済を求めている場合は、緊急に支援が必要な状況だということです。児童相談所への通告が第一選択肢ですが通告先に迷うときは、子ども未来課へご相談ください。保護者の同意は問われません。
緊急の支援が必要な状況に至っていない場合でも、自尊心を傷つけられると、自分のことを尊重できなくなり否定的にとらえるなど心理的影響は大きく、他者とのコミュニケーションが消極的で信頼関係を築きにくいなど、将来的に個人の社会性に影響を及ぼします。
- 落ち着きがない・怒りっぽい
- 表情が乏しく、ボーっとしている
- 先生やお友達の親への過度なスキンシップや密着
- 自暴自棄な言動や大人を試すような言動がある
などの行動として表れることがあり、虐待の影響が疑われます。
また、発達の問題との見分けが難しいことも多くあります。こどもの発達の問題が保護者の関わりの難しさにつながり虐待行為となっている場合は、こどもの発達の問題が解明されれば虐待が解消されることもあります。
気になる様子がある場合は、虐待の影響か発達の問題かを悩み通告が遅れることがないよう、家庭支援の視点をもって子ども未来課に対応をご相談ください。
家庭・保護者の様子

- 些細なことで激しく怒るなど、感情のコントロールむずかしい
- きょうだいに対しての差別的な言動・服装や持ち物に差がある
- 理想の押し付けや年齢や発達段階に合わない要求をしている
- 厳しいしつけ・行動制限をしている
- 夫婦間の口論や絶え間ないケンカ
- 家族や同居人との不和
などがある場合は、心理的虐待となっている可能性があります。
養育されていない、育児放棄があるかも
栄養状態や育児状況が心配
栄養失調や治療を受けさせないなどがあり、生命・身体の安全に関わるネグレクトがあると疑われる場合は、児童相談所または警察への通告が第一選択肢です。
児童相談所や警察への通告を迷うときは、子ども未来課へご相談ください。保護者の同意は問われません。
こどもや保護者の様子
保護者の養育に関する知識不足や経済的問題、保護者・養育者の不在(傷病、家出、死亡など)により、育児放棄の状況に至っている場合もネグレクトに含まれます。

- 衣服を着替えさせない…いつも同じ服をきていたり、身体や衣服の汚れがないか
- 食事を充分に与えない…機嫌がわるい、食欲が異様、脱水症状がないか
- こどもを家に残して外出する・家に閉じ込める…欠席の傾向がないか(欠席連絡の有無・欠席の理由・不自然な長期休暇等)
- 保護者の言動…子育ての手技に困っていることはいないか、家計や生活、健康面の悩みがないか(子育ての協力者の有無・支援情報を知っているか・支援を求めることができるか等)
などを日頃から観察しましょう。
特に、乳幼児の低体重(成長曲線-2DS以下)、栄養失調、衰弱、脱水症状、医療放棄、治療拒否は、死亡リスクが高いため注意を払う必要があります。
性的虐待を受けているかも
こどもから性的虐待の訴えや匂わす言動を聞くなどした
性的虐待には、こどもへの性交や性的な行為を強要・教唆、こどもの性器や性交を見せるなどがあげられます。また、直接の行為がなくても児童ポルノの被写体にする行為も性的虐待に含まれます。
性的虐待は、本人が告白するか、家族が気づかないと顕在化されません。「話したらころすぞ」などと脅されていたり、開始年齢が早いとこどもは性的虐待だと理解できないこともあります。
こどもから訴えや匂わす言動があった場合は、児童相談所または警察への通告が第一選択肢です。
児童相談所や警察への通告を迷うときは、子ども未来課へご相談ください。保護者の同意は問われません。「そんなことが起こるはずがない」と思いがちですが、実際に乳幼児期から発生していますので先入観は禁物です。
虐待が疑われる時に気を付けること
こどもからの聞き取り
いつ・誰に・何をされたのかのみ確認をし、こどもが自分から話さない場合は、頑張って訴えを聞き出すことは不要です。根掘り葉掘り聞きすぎると、答えているうちに記憶の汚染が起こり、体験した出来事についての記憶が変わってしまうことがあります。詳しい調査は、担当の職員が行います。
身体に外傷がある場合は、可能な限りこどもに了承を得た上で外傷の状況がわかるよう写真を撮るなど記録をしておきましょう。
保護者への支援
家庭の様子が心配な保護者に対し、学校などでのこどもの様子を伝え家庭での困り感などがないか声をかけましょう。
例えば、「最近落ち着きがないのですが、おうちではどうですか?」
「かんしゃくがあるので、おうちでも困っていないか心配です」
「お友達とうまくいかないことが多いのですが、きょうだいとはどうすか?」
など「いつもこどもを見守っている」「こどもや家庭を心配している」というメッセージが伝わるように声をかけましょう。
声をかけた時の保護者の反応は、反応しない・事実の否定・こどもを嘘つき扱いする・怒りをぶつける・困り感を打ち明けるなど、様々です。声かけに応じない場合でも、それだけ困難さがあるのだと捉え、保護者の気持ちに寄り添い、一緒に考え対応していくことを伝え子ども未来課など専門機関への相談を勧めましょう。








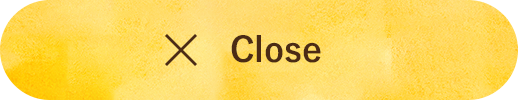


更新日:2025年04月11日