児童虐待予防のためにできること
こどもや保護者からSOSを出しやすくするために
日頃からの見守り
虐待の加害者は、凶悪な犯罪者ではなくごく普通の親であることが大多数です。
児童虐待となるのを予防するためには、どの家庭でも虐待は起こり得るという認識に立ち、こどもや保護者に気になる様子はないか、支援を要する状況はないかなど、家庭支援の視点をもち見守ることが重要です。
子育て中の家庭について問題を探したり疑うのではなく、あたたかいまなざしで見守り、気になる様子があれば支援につなぐよう声をかけましょう。声をかけるのがむずかしい場合は、抱え込まず子ども未来課までご相談ください。
こどもの異変や違和感
- 表情が乏しい・持続的な疲労感・無気力
- 触られること・近づかれることをひどく嫌がる、逆に過度なスキンシップを求める
- 乱暴な言葉遣い・極端に無口
- 説明できない不自然なケガや繰り返すケガ
- 大人への反抗的な態度や大人の顔色を窺う態度
- 親子でいるときには親を窺う態度や表情が乏しいが親がいなくなると急に表情が晴れやかになる
- 体育や身体計測のときによく欠席する
- 低身長や低体重、体重減少
- 落ち着きがない・教室からの立ち歩き・集中困難な様子
- 家に帰りたがらない
- 性的に逸脱した言動
- 異様な食欲
- 衣服が汚れている など
悩みを抱えているかもしれない保護者の様子
- 感情や態度が変化しやすく、余裕がないように見える
- 表情が硬い・話しかけても乗ってこない
- こどもへの近づき方やこどもとの距離感が不自然
- 連絡が取りにくい
- 人前でこどもを厳しく叱る・叩く
- 行事に参加しない
- 家庭訪問・懇談などのキャンセルが多い
- こどもが具合が悪くなったなどで保護者に連絡しても緊急性を感じていない
- 家庭の様子が見えない など
支援を要する家庭の状況
- 乳幼児がいる
- こどもの生来的な気質による育てにくさがある
- こどもの問題行動(盗み、虚言、自傷他害など)
- 生育上の問題(未熟児、慢性疾患、障がい、発育・発達の遅れ)
- 複雑な家族構成・親族以外の同居人がいる
- 保護者の成育歴の問題(虐待を受けた経験がある、何らかのトラウマがある)
- 養育技術(知識、能力、危機管理など)が未熟
- 養育の支援者や協力者がいない
- 望まない妊娠・出産・無計画な多子
- 社会的に孤立している
- 経済的な問題 など
いろいろな相談窓口
気になる様子があるときは、抱え込まずに相談しましょう。
- スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど…所属の学校に相談しましょう。
- 24時間こども相談ダイヤル 電話:0120-078310 ※24時間年中無休
- こどもの人権110番 電話:0120-007-110 ※平日8:30~17:15
- 児童相談所虐待対応ダイヤル 電話:189 ※24時間年中無休
- 児童相談所相談専用ダイヤル 電話:0120-189-783
- 親子のための相談LINE(こども家庭庁LINE official account)
- 子ども未来課 子ども家庭係 電話:0192-54-2111 ※平日8:30~17:15
こどもが訴えられる年齢になれば、こども自らが相談しやすくなるような体制を整えることも大切です。
学校などのこどもが所属する機関では、複数の窓口を常に教室や廊下などに掲示したり、保護者に定期的にお知らせするようにしましょう。
『マルトリ』にならないために
『マルトリ』ってなに?
最近ではこどものしつけで気を付けたいポイントとして、「マルトリ」ということばを見聞きすることも増えてきているのではないでしょうか。
『マルトリ』とは、マル(=わるい)トリートメント(=扱い)の略称です。
1980年代からアメリカなどで広まった表現で、日本語で『不適切な養育』と訳され、こどもの健全な発育を妨げるとされています。WHOでは、「身体、精神、性虐待そしてネグレクトを含む児童虐待をより広く捉えた、虐待とは言い切れない大人からこどもへの発達を阻害する行為全般を含めた不適切な養育」と定義づけています。
虐待とほぼ同じ意味ですが、「こどものこころと身体の健全な成長・発達を阻む養育をすべて含んだ呼称」であり、保護者であるかや大人の側に加害の意図があるか否かにかかわらず、また、こどもに目立った傷や心理的影響が見られなくても、行為そのものが不適切であれば、マルトリートメントと言います。
保護者や子育て世代の問題にせず、こどもの未来を守るために地域全体で『マルトリ』にならないよう心がけましょう。
マルトリートメントの概念(イメージ図)









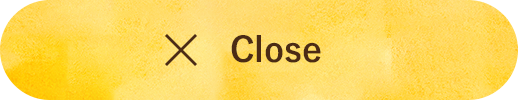

更新日:2025年04月11日